はじめに|あなたはどっち派?速く読みたい?深く読みたい?

「本を読みたいけど時間ないし、内容を頭に残らない…」
こんな悩み、抱えたことはありませんか?
そんなとき、よく耳にするのが「速読」と「熟読」。
けれど、「どっちが正解なの?」「自分に向いてるのはどっち?」と、かえって迷ってしまう人も多いはずです。
本記事では、速読と熟読の違いやメリット・デメリット、本のジャンル別におすすめの読み方まで、わかりやすくご紹介します。
自分の読書スタイルを見直し、“量も質も満たす”読み方を一緒に見つけていきましょう。
▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼
\ ”持ち運べる読書”試してみませんか? /

そもそも「速読」と「熟読」ってどう違うの?
- 速読:重要なポイントをすばやく拾いながら読む技術。情報収集向き・
- 熟読:一文一文に集中し、深く理解する読み方。思考・感情を伴う体験型
- 通読:全体の流れをつかむために、一度サラッと読む方法。速読と熟読の中間
言い換えれば、
「速読=広く浅く」
「熟読=狭く深く」
どちらも、目的によって力を発揮する異なるスキルです。
速読のメリットと使いどころ
- 情報の取捨選択が早くなる
- ビジネス書、自己啓発書、ライトなエッセイに向いている
- 読書量が増えて、インプットの幅が広がる
特にビジネスパーソンにとって、「読むか読まないか」を瞬時に判断する力は重宝します。
「本の価値を見極める」前段階として、速読は強い味方です。
ただし、理解の深さや記憶への定着は弱くなりがちなので、読み流すだけでは満足できない人には物足りなさも残るかもしれません。
熟読のメリットと使いどころ
- 内容がしっかり頭に残る
- 思考力や語彙力、表現力が自然と鍛えられる
- 難解な本、小説、古典との相性がいい
熟読は「読書=体験」として味わいたい人にぴったり。
行間を読む楽しさ、余韻にひたる時間、物語の中で感情が動く感覚…。
こうした“本との対話”ができるのは、やはり熟読の魅力です。
読む本によって、読み方を変えていい
正直なところ、どちらか一方だけを使う必要はないと思っています。
| 📖本の種類 | 向いている読み方 |
| 🔵ビジネス書、実用書、情報本 | 速読または通読で効率よく |
| 🔵小説、古典、哲学書 | 熟読でじっくり味わう |
| 🔵雑誌、エッセイ、WEB記事 | 状況に応じて柔軟に |
「とりあえず速読してみて、気になる本だけ熟読する」というスタイルも、無理なく読書を続けるコツですよ!
速読+熟読の”いいとこ取り”術
おすすめなのは“三段階読み”。
- 超速読:目次・見出し・冒頭と結論だけサッとチェック
- 速読:一通り読んで概要を把握
- 熟読:気になった箇所を、あとからじっくり読む
この流れをクセづけると、
・つまらない本に時間を使わずに済む
・必要な本は深く理解できる
・自分の読書スタイルが安定する
と、まさにいいとこ取りができます。
実践!今日からできるトレーニング法
✅速読トレーニング|情報をすばやくキャッチできる力を磨く
● ステップ①:目次から全体構成をつかむ
- まず本を開いたら、目次と章タイトルに3分集中。
- 「この章では何を言おうとしているのか?」を自分なりに予測してみましょう。
- 各章に1文ずつ「○○について書かれていそう」とメモをすると◎。
▶例:「第3章 結果を出す人の朝習慣」👉「早起きやルーティーンの話かな?」
● ステップ②:冒頭と末尾だけを読む
- 各章の最初と最後の段落(導入とまとめ)を読むだけで、内容の要点が見えてきます。
- 繰り返されるキーワード、強調された表現(太字・箇条書き)を意識すると、著者の主張がつかみやすくなります。
● ステップ③:要点にマークする(線引きは目的別に)
- すべてに線を引くと逆効果なので、「目的別の線引きルール」を決めると効率アップ。
| マーカー色 | 意味 |
| 黄色 | キーワード・主張 |
| 青色 | 行動のヒント・ノウハウ |
| 赤色 | 自分に刺さった言葉 |
※マーカーを使いたくないという人は、付箋やページ折りでもOKです✨
✅ 熟読トレーニング|本の中を深く“旅する”読み方
● ステップ①:ペンを片手に“書き込みながら読む”
- ノートにメモを取るのではなく、本そのものに直接書き込むスタイルが効果的(中古本では控えめに)。
- 気になった文章には→!や?、共感した部分には→♡や◎など、自分なりのマークを使うと読書がもっと楽しくなります。
● ステップ②:問いかけをしながら読む
- 「なぜこう言ったのか?」
- 「これは自分にどう関係ある?」
- 「似た体験はあったかな?」
という問いを立てながら読むと、理解がぐっと深まります。
● ステップ③:1ページに10分かけてもOK
- 特に小説や哲学書、詩集などでは「速く読む」よりも「味わう」ことが大切。
- たとえば、印象的な一文をノートに写すだけの日をつくっても、読書の質は高まります。
✅ 読書を補助してくれるツール&工夫
● flier(フライヤー):10分でビジネス書を把握できる要約サービス
- 要約された本のエッセンスを事前に読めば、「自分が本当に読みたい本か?」を見極める手助けに。
- 時間がないときは、flierで概要をつかみ、必要なら熟読に進むという使い方も◎。
- 一部無料。有料プラン(月額500円~)では新刊要約も読めます。
● マンガ版での導入
- 「難しそう…」と感じる本でも、マンガ化された入門版を先に読むことで心理的ハードルがぐっと下がります。
- ビジネス書・哲学書・自己啓発書など、多くの名著に漫画版があるので活用しやすいです。
▶例:「嫌われる勇気」「7つの習慣」「思考は現実化する」などは人気の漫画版あり!
● 音声・動画で“前読み”する
- YouTubeやPodcastで本の要約を聴いたあとに原著を読むと、理解のスピードが格段に上がります。
- 特に通勤・家事中の「ながら時間」に活用できるのが便利。
まとめ:トレーニング×補助ツールで”読書筋”を鍛えよう
▶「読書が苦手」「時間がない」そんな人こそ、読み方の工夫をするだけで驚くほど変わります。
- 速読で”広く読む”力を磨く
- 熟読で”深く読む”感性を育てる
- 補助ツールで読書を”ラクに・楽しく”する
読書に「正解」ってありませんよね。
大事なのは「自分に合ったやり方で、読み続けること」
今日からぜひ、気になる本でこの3つのアプローチを試してみてくださいね🌱
.png)


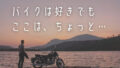
コメント